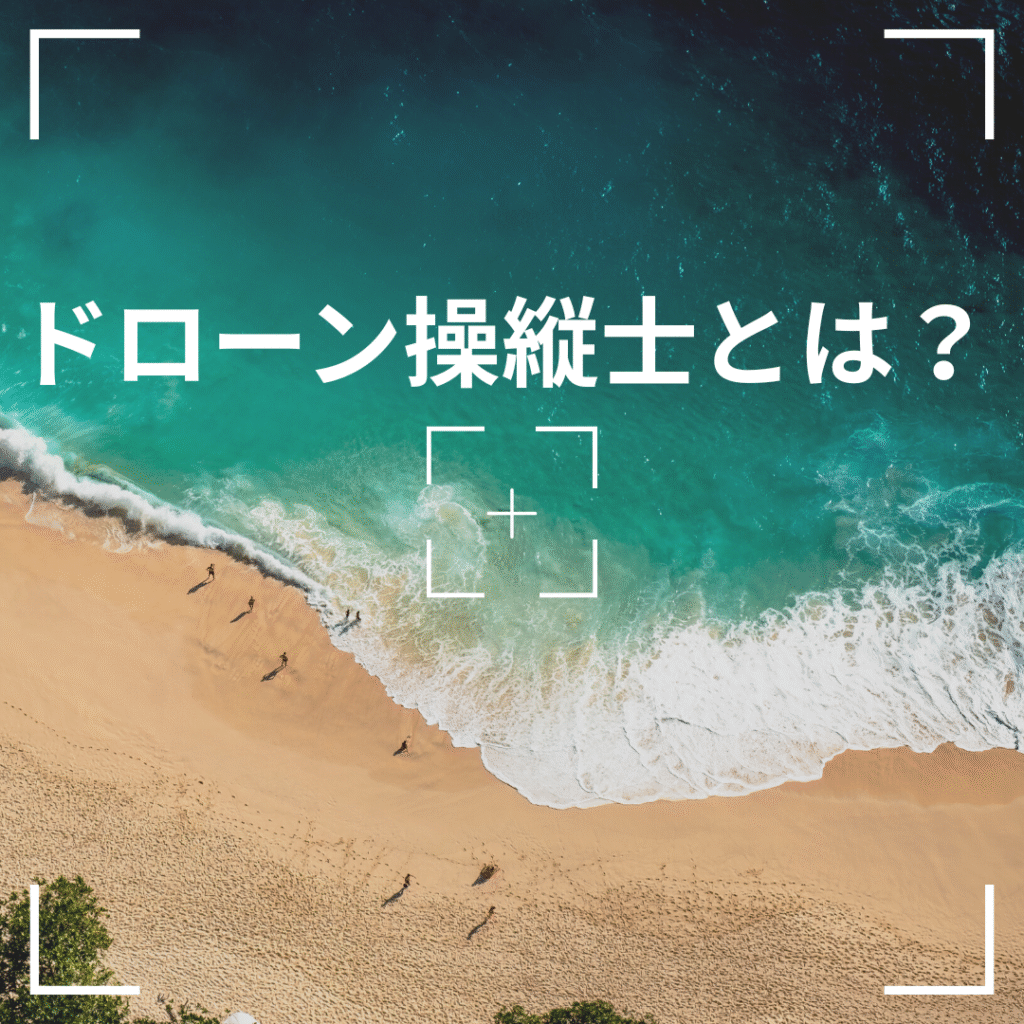
はじめに:空を舞台にした“未来型職業”の登場
「ドローン操縦士」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか?
空撮映像を撮る人?それとも災害現場で活躍するレスキュー隊?
実は今、ドローン操縦士という職業が、20代の若者にとって“新しい手に職”として注目されています。
テクノロジーの進化とともに、空を使った仕事が現実のものとなり、映像制作から農業、物流、災害対応まで、ドローンの活躍の場は急速に広がっています。
そしてその操縦を担う「ドローン操縦士」は、専門性と社会貢献性を兼ね備えた、まさに未来型の職業なのです。
ドローン操縦士の仕事内容とは?
ドローン操縦士の仕事は、単に機体を飛ばすだけではありません。
目的に応じて、正確かつ安全にドローンを操作し、必要なデータや映像を取得することが求められます。
主な業務内容は以下の通りです:
- 空撮・映像制作:映画、CM、観光PR、YouTubeなどの映像コンテンツ制作
- 測量・点検:建設現場やインフラ(橋梁・ダム・送電線など)の点検・測量
- 農業支援:農薬散布、作物の生育状況のモニタリング
- 災害対応:被災地の状況把握、捜索活動、避難誘導支援
- 物流:離島や山間部への物資輸送(実証実験が全国で進行中)
これらの業務には、操縦技術だけでなく、航空法や安全管理、機体整備、データ処理などの知識も必要です。
つまり、ドローン操縦士は「空の技術者」であり、「現場の課題解決者」でもあるのです。
国家資格で信頼性アップ:「無人航空機操縦者技能証明制度」
2022年12月、日本ではドローン操縦に関する国家資格制度がスタートしました。
それが「無人航空機操縦者技能証明制度」です。
この制度では、操縦士の技術レベルに応じて以下の2種類の資格が設けられています:
- 一等操縦士:目視外飛行や有人地帯での飛行など、高度な業務に対応
- 二等操縦士:基本的な業務飛行に対応(空撮、測量など)
資格取得には、国土交通省が認定する登録講習機関での座学・実技講習を受け、学科試験・身体検査に合格する必要があります。登録講習機関で受講する事によって実地試験が免除されます。また、登録講習機関の講習を受講せずに、指定試験機関での飛込試験に合格し、学科試験・身体検査を受検し国家資格を取得する方法もあります。
なぜ今、20代におすすめなのか?
ドローン操縦士は、男女関係なく活躍する事が出来る職業です。飛行技術だけでなく、関連する仕事、例えば空撮データを編集しPR動画の作成を行う場合、ドローン以外の専門知識や技術面も身に付ける事が可能な環境下にありますので、転職する際にも業種の幅が広げやすくなります。
特に20代の若者にとっては、以下のようなメリットがあります:
- 未経験からでも始められる:講習と練習でスキルを習得可能
- 就職活動で差別化できる:国家資格は履歴書に書ける強み
- 副業・フリーランスにも対応:空撮やイベント撮影など個人で仕事を受けられる
- IT・映像スキルとの相性が良い:編集・解析などのスキルと組み合わせて活躍の幅が広がる
- 社会貢献性が高い:災害対応や地域支援など、社会に役立つ仕事ができる
また、若いうちからドローンに触れることで、技術の習得が早く、柔軟な発想で新しい活用方法を見出すことも可能です。
ドローン市場の未来とキャリアの可能性
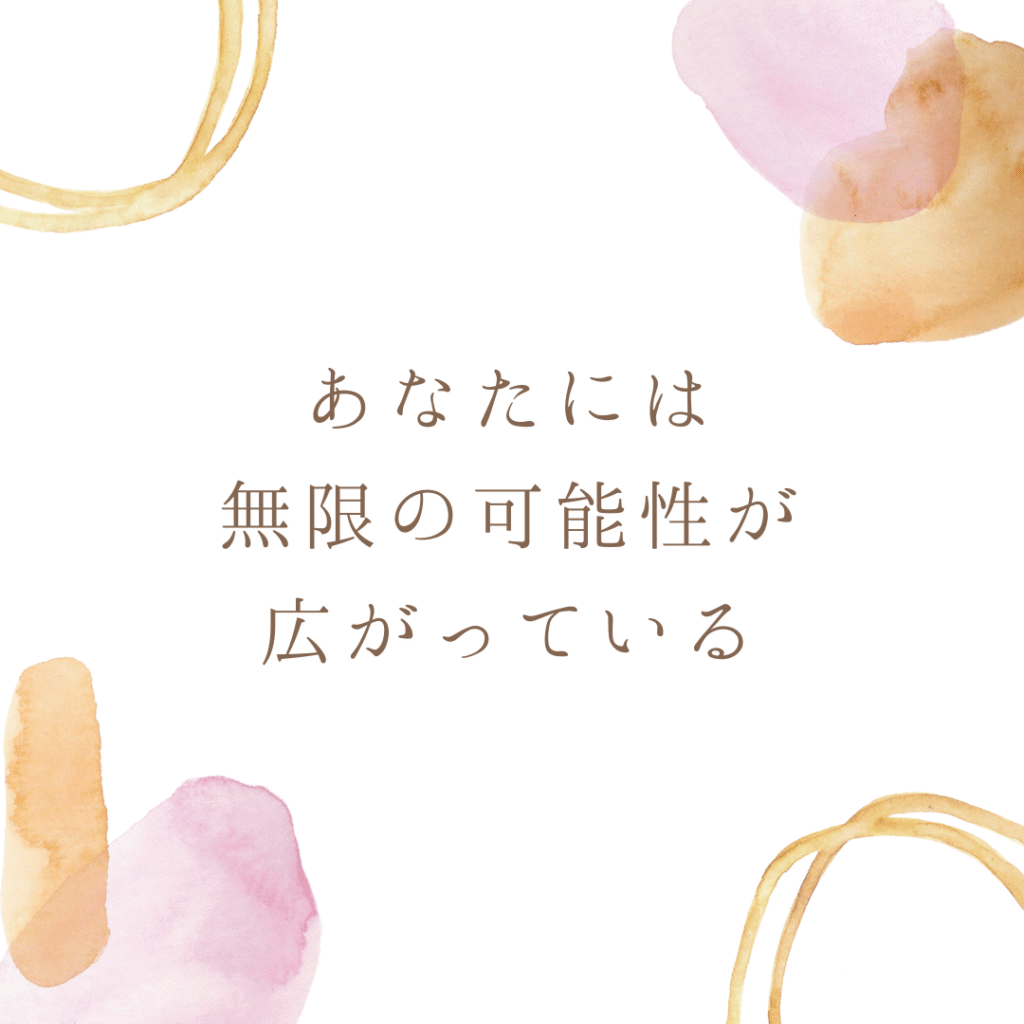
経済産業省の調査によると、日本のドローン市場は2022年時点で約3,000億円規模でしたが、2026年には約6,000億円規模に達すると予測されています。
この成長の背景には、以下のような要因があります:
- 災害対応・インフラ点検のニーズ増加
- 自動運転・AI連携によるスマートドローンの普及
- 地方自治体や消防・警察による導入拡大
- 国際的な技術連携(例:トルコのBaibars社製消火用ドローンなど)
ドローン操縦士は今後ますます必要とされる職業であると言われています。ドローンが急速に普及される事で、パイロット不足に陥るとも言われています。
ドローン操縦士になるためのステップ
- 講習を受ける
国土交通省認定の登録講習機関で、操縦技術や法律、安全管理などを学びます。 - 国家資格を取得する
「無人航空機操縦者技能証明」の一等または二等資格を取得することで、業務での操縦が可能になります。 - 実務経験を積む
アルバイトやインターンなどで実務経験を積み、スキルを磨きましょう。 - 専門分野を見つける
映像、測量、農業など、自分の興味や得意分野に合わせて専門性を高めることが重要です。
まとめ
これからの仕事のひとつとしてドローン操縦士になる為の解説をしました。まだまだ伸びしろのある産業であることは間違いないと思います。我々も日々創意工夫をしながらサービス展開をしています。ドローンがもっと皆様にとって身近な存在になり、産業の発展はもちろん社会貢献へ繋がるツールとして活躍出来るように活動を続けていきたいと思います。





